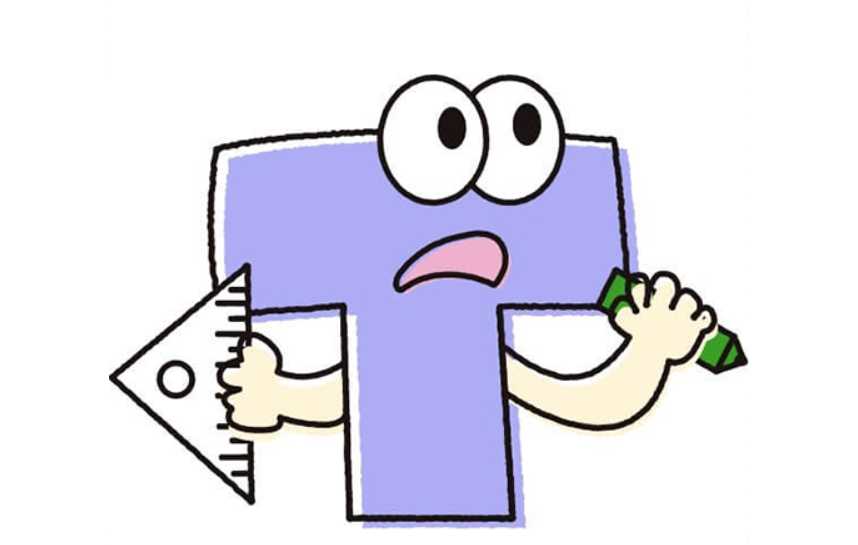- 作図システムはどれを使ったらいいの?
- 作図システムを使いこなすのは難しい。
このようなお悩みがありませんか。
正確に相続税額を計算するためには、土地の評価額を正しく算出できるかが重要なポイントの一つです。
さまざまな土地作図システムを使った経験を基に、税理士の私がおすすめする4社のシステムをフクモト税理士とともにご紹介します。
おすすめの4社の作図システムの機能比較
実務上難しい土地評価のポイント4つ
まず、各社の特徴と作図システムを使う上での実務上の難しいポイントを解説します。
そのうえで税理士2名がおすすめする土地作図システムを実際に操作しながら、商品レビュー(比較)していきます。
動画では実際のシステムの画面で操作方法をわかりやすく解説しているため、実際の操作感がわかりやすくなっています。
こちらの動画も合わせてご覧ください。
おすすめの作図システム4選

おすすめの作図システムを4つのカテゴリーに分けました。
カテゴリーAの左3つは大手3社で、2つは大手ではない会社です。
このカテゴリーのシステムは土地評価明細とすべて連動しており、ほぼ機能の差別化はありません。
その中で一番のおすすめは、株式会社NTTデータが提供する「財産評価の達人」です。
カテゴリーB「陰地名人」(かげちめいじん)は、市場シェアが一番大きい有名なソフトです。
カテゴリーC「AP-CAD」は、土地の作図に必要な基本的な機能をほぼすべて網羅しており、おすすめです。
カテゴリーD「土地作図君」は、実務で土地作図に必要な機能をすべて網羅しており、私も関与しているおすすめのシステムとなります。
本記事では作図システムを皆様に認知していただくため、各社のシステムをあくまでも客観的に俯瞰してカテゴリーA~Cを中心に説明していきます。
土地作図システムを使う上での難しいポイント4つ

- 土地の評価方法により手作業が発生する
- 土地の評価単位の分割が難しい(どこで分割するのか)
- 手作業の部分があるため、正確性に疑問が残る場合がある
- 現地調査は必須
1.土地の評価方法により手作業が発生する
1つ目は土地をどのように評価方法によっては、手作業が発生してしまう場合があります。
例えば、2つ以上の地番を一体として評価する場合、手作業が必要となります。
測量図が2つ以上あって、その上に建物がある場合は、その測量図をふたつ重ねて一体として評価する場合です。
陰地名人やAP-CADは対応できますが、前処理が結構必要となり、作業が煩雑になりがちです。
しかし、実務的にはこのような地番が2つ以上の土地を一体評価するケースは頻繁にあります。
2.土地の評価単位の分割の難しさ
2つ目は、土地の評価単位の分割の難しさです。
たとえば、一つの地番でマンションが何棟かあるケースです。
そのときにどこで土地を分割するかはなかなか難しい場合が多く、分割地点を決めるのに、実際に現地に見に行くまたは建物の平面図を確認します。
しかし、平面図も結構実際とズレてる場合も多いでしょう。
そこで、建築確認概況書を見て、現地に行ってポイントを測量して、決めていきます。
3.正確性に疑問が残る場合がある
3つ目は、手作業の部分があるため、正確性に疑問が残る場合がある点です。
現況と図面と違っているケースは、やはり手作業が多くなり、正確を期すのは難しい場合もあるでしょう。
実務的にはやはりウォーキングメジャーとか手巻きメジャーでの測量が多くなり、アイカ工業株式会社製のレーザーポインターで距離を測る場合もあります。
測量の専門家ではない税理士が行う測量はこのあたりが限界となるでしょう。
実際、税理士の現地測量と図面の測量に差異が生じているときもあり、職業倫理として税理士が面積を修正してもよいのか迷う場合も往々にしてあり、どちらで計算するか迷うケースもあります。
また、ある程度は税理士でも測量できますが、本当にどこまで厳密にできるのか疑問が残ります。
税理士としては、もっと正確にできた方望ましいですが、土地の評価額はほんの少しの点のズレで変わってしまいます。
だからこそ、手作業では手巻きメジャーで測れば正確かもしれませんが、手作業での測量が難しい土地もあります。
土地の広さ200㎡ぐらいでしたら対応できますが、1,000mを超えるような広大な土地を手巻きメジャーで測量するのはわかりにくくて現実的ではありません。
この点では、今回取り上げている「土地作図君」のシステムとドロガー(測定機器)が連動しています。
「土地作図君」は座標点を取れるため、簡易測量に近い形になるのではないでしょうか。
とくに測量図がない広大な土地には適しているでしょう。
測量図がない土地は、あらかじめGoogleであたりをつけて現地で確認するのが一般的な流れとなっています。
それでも、結局は手巻きメジャーやウォーキングメジャーでの現地測量となるため、Googleに頼らざるおえないのが実情かもしれません。
ただし、最近のGoogleは精度が上がってきており、さまざまな角度から見られるようになってきています。
4.現地調査は必須
4つ目は現地調査が必須となる点です。
とくに土地の境界線はGoogleではわからないため、現地調査が必須です。
現地で境界線を見て確認しますが、実際、現地をみてもわからない場合があり、難しいところです。
おすすめ作図システム比較一覧表

| NTT財産評価 | 陰地名人 | APCAD(税理士向け簡易CADソフト) | 土地作図くん | ||
| ① | 料金 | 月額課金21,900円/年(税別)~42,700円/年(税別)+オプション13,500円(税別)=35,400円/年(税別)~56,200/年(税別)→2,950円/月(税別)~4,683円/月(税別) | 月額課金システム利用料600円/月(税別)会費3,000円/月→~4名まで(4ID発行)/1事務所=合計3,600円/月(税別) | 買切50,000円(税別)※1ライセンスで職員の皆様が使用可能 | 月額課金システム利用料30,000円/年(税別)→2,500円/月(税別)1ライセンス1ID同時ログイン不可 |
| ② | アプリ or クラウド | インストール | インストール | インストール | クラウド |
| ③ | 評価明細書連動 | 〇自動で連動※制約が多くなる | ×できない | ×できない | ×できない |
| ④ | マニュアルの整備 | △動画説明あり | △動画説明あり | ×文字で説明 | 〇動画説明あり |
| ⑤ | 直観的作業 | 〇わかりやすい | △わかりにくい | ×かなりわかりにくい | 〇わかりやすい |
| ⑥ | 土地の図面の読込ファイル形式 | 〇PDFや画像データに対応画像はきれい | △PDFのみ画像があらい | △画像データのみ読込 | △PDFのみ画像はきれい |
| ⑦ | 印刷時に縮尺変更 | ×できない | ×できない | ×できない | 〇できる |
| ⑧ | 土地を分割 | ×できない | 〇できる | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑨ | 参考図図面を基に土地を分割 | ×できない | ×できない | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑩ | 複数の測量図を重ねる | ×できない印刷時に貼り合わせする | ×できない印刷時に貼り合わせする | ×できない印刷時に貼り合わせする | 〇できる |
| ⑪ | 土地の任意の分割 | ×できない | 〇できる | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑫ | 陰地のパターン出しアシスト | 〇できる | ×できない | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑬ | セットバック | 〇できる | ×できない | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑭ | 無道路地 | △できるが、一定の機能のみ | △一定の土地についてはできるが、操作が難しい | △できるが、操作が難しい | 〇できる |
| ⑮ | 測量図のない土地について | ×対処法なし | ×対処法なし | ×対処法なし | 〇一定の土地については可能 |
| ⑯ | システム内でのデータ保存 | ×できない | ×できない | ×できない | 〇ウェブ内に保存可能 |
| ⑰ | 所感 | ・メリット 評価明細書との連動を重視するならおすすめ。整形地や、単純な土地ならおすすめ。 ・デメリット 補正ができない。トリミング時の面積を採用。 | ・メリット 操作方法はわかりやすい基本的な土地なら問題なく利用できる。 ・デメリット 補正がいまいち評価明細書と連動できない | ・メリット 必要最低限度のことができて、おすすめ。 ・デメリット 操作方法が煩雑で操作説明がわかりにくい評価明細書と連動できない | ・メリット 操作方法がわかりやすい複雑な土地に対応できる ・デメリット 評価明細書と連動できない |
おすすめ作図システムの商品レビュー(比較)

以下、おすすめの4つのシステムです。
- 財産評価の達人
- 陰地名人
- AP-CAD
- 土地作図君
それでは、それぞれのシステムを操作しながら解説します。
1.財産評価の達人
「財産評価の達人」は、財産cubeの税務申告ソフトシリーズのひとつです。
財産cube内の「財産評価の達人」のソフトを起動させ、新規作成メニューからはじめます。
任意の財産コードを入力し、業務メニュー→土地の評価明細書の作成→「土地および土地に存する権利」メニューをクリックします。
財産の選択から先ほど作成した財産コードを選択します。
オプションメニューになりますが、帳票選択→かげ地割合計算をクリックし、共有割合を入力してから画像を取り込みます。
そこから手作業でトリミングしていきます。
隅切り、セットバックの設定ができますが、面積から距離を計算すると、ズレが生じ、補正機能がありません。
土地評価明細と連動しており、作図すると、自動的に土地評価明細を作成できます。
2.陰地名人
操作手順は上記の「財産評価の達人」と同じです。
新規作成から画像を取り込んで作図していきますが、画像が荒く、見にくいうえに拡大しても文字が読み取れません。
面積をもとに一辺の基準尺を決め、基準尺を設定すると、次はトリミング作業をしていきます。
すべての辺を決め、面積を補正していきます。
補正パターンは3パターンできますが、全体が大きく変わってしまう場合があるため、一部を補正したい場合には注意が必要です。
隅切り機能があり、辺の距離が測れるのと1つの土地を分割できるため、1つの土地に建物が複数建てられているケースでは便利です。
ただし、2筆以上の土地を一体として評価する機能はありません。
3.AP-CAD
こちらは画像データが(JPG)しか取り込みできませんが、トレースモードで補正できます。
トリミング作業は他のシステムと同様です。
自動計算された面積を変えると大きさを変えられ、辺は1つずつ選んで変更します。
また、下図を表示させないことも可能です。
AP-CADはシステム上で測量図2つを合体できますが、手間がかかるため、手作業で重ね合わせてから作業するのがおすすめです。
上記2つのシステムよりもできる作業は多くなりますが、操作は難しくなっています。
4.土地作図君
他のシステムと同様に画像データの取り込みからトリミング作業をしていきます。
面積が違っている場合は面積が自動計算され、辺も計算されます。
セットバックや隅切りなどの基本的な作図機能はすべて網羅されています。
「土地作図君」と他のシステムとの違いは、実務で必要となるさまざまな機能が盛り込まれているところです。
1つ目は、ドロガーで取得した座標データをGPX編集メニューで取り込みが可能で、現地調査のデータを作図に直接反映できます。
座標データを取り込むと複数の頂点がでてくるので、不要なデータを削除し、作図できます。
2つ目は、縮尺の設定や建物の図面のアップロードが可能で、土地の分割、測量図2つ以上を重ねるのも可能となっています。
操作マニュアルも動画で確認でき、土地評価に詳しくないスタッフでも取り扱いが簡単です。
ただし、土地評価明細とは連動していませんので、ご注意ください。
おすすめ4社のシステム比較【まとめ】

単純な土地の評価をする場合は大手企業が提供する「財産評価の達人」、「陰地名人」がおすすめです。
操作が単純で土地評価明細にも連動しているため、土地評価に詳しくないスタッフでも取り扱いが簡単です。
ただし、複雑な土地の評価には対応していないため、相続税の土地評価を頻繁に行う場合は利用しにくいでしょう。
「AP-CAD」は、料金体系もリーズナブルで、基本的な機能はすべて網羅しているため、相続税の基本的な土地評価全般に対応できます。
ただし、土地評価に詳しくないスタッフでは操作が難しいところがデメリットでしょう。
「土地作図君」は、操作がわかりやすく複雑な土地にも対応できるため、相続税の土地評価全般に対応できます。
また、他のシステムにはないドロガーで測定した座標からの作図や2筆以上の土地を一体として扱えるのも大きなメリットです。
ただし、土地評価明細とは連動していないため、ご注意ください。
作図システムは複雑な土地評価の手間を減らしたい、作業の正確性や効率性をあげたいときにぜひご検討ください。
本記事を参考にご自分の実務に合った作図システムを選びましょう。